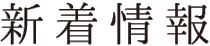 news
news
ARCHIVES
大日如来像「THE FIRST BUTSUZO」公開のご挨拶
2025.10.11
十五年の祈り、ついに結実――大日如来像「THE FIRST BUTSUZO」公開のご挨拶
本日10月11日、構想から足掛け十五年におよぶ歳月をかけて造立を進めてまいりました
「空海の幻の大日如来像」が、ついに讃岐国分寺において開眼・公開の日を迎えました。
この像は、全国の寄付者の皆さま、制作に携わった工房スタッフの皆様、彩色と仏画でご尽力いただいた塩崎顕先生、
お堂の修理と補強を堅実にしていただいた小比賀工務店様、内装設計を考えて頂いた成瀬猪熊建築設計事務所様、その施工と困難な組み立てを完遂していただいた菅組の現場監督、松本進様、工事関係者の皆様、強制執行による回収を手伝っていただいた澄星月堂様、
そして三度のクラウドファンディングを通じて孤独な勧進を陰に日向に支えてくださった
デザイン事務所ハレノシタクのデザイナー宮間晴香様をはじめとする多くの方々の力によって、
ようやく完成の時を迎えることができました。
この十五年の道のりは、決して平坦なものではありませんでした。
構想、製作、資金集め、そして幾多の困難――
しかし、そのすべてを怒りではなく祈りと信念の力に変え、歩み続けてきました。
この像は、まさに「祈り」と「信念の勝利」の象徴です。
発願の原点は、一人のお父さんとその娘さんの姿でした。
深い悲しみの中でなお生きようとする人々へ、
「この世界は生きる価値がある」と伝えたい。
その思いこそが、この仏像を生んだ出発点でした。
この像に込めた祈り――
『この世界は生きる価値がある。あなたの人生は生きる価値がある。』
そしてこの大日如来は、あなたも私も、
あのお嬢さんも、そのお父さんも、すべてが同じひとつの命であることを示しています。
この宇宙全体がひとつの生命であるという真理を形にしたものです。
ご寄付くださった方々もまた、この像の創り手の一人です。
亡くなられたご家族の思いも、この像の中に永遠に息づいています。
この仏像は、芸術と信仰、思想と技術、祈りと科学――
そのすべてが交わって生まれた「人類の至宝」であり、
仏教美術2500年における新たな到達点となりました。
この日を迎えることができたのは、皆さまお一人お一人のご支援のおかげです。
心より深く御礼申し上げます。
どうかこの像を前に、
「ああ、この世界にはまだ美しいものがある」
「生きていてよかった」
そう感じていただければ、それが何よりの報いです。
――――
この世界は生きる価値がある。
あなたの人生は生きる価値がある。
合掌
讃岐国分寺 住職 大塚純司九拝
特設ページ公開と寄付者特別拝観ご案内のお知らせ
2025.10.01
特設ページ公開と寄付者特別拝観ご案内のお知らせ
このたび、讃岐国分寺の新たな挑戦「THE FIRST BUTSUZO」プロジェクトの特設ページを公開いたしました。
特設ページでは、空海の言葉「密蔵は深玄にして翰墨に載せ難し。さらに図画を仮りて悟らざるに開示す」を思想的基盤とし、十数年の歳月をかけて完成した大日如来像の全容をご紹介しています。
-
プロジェクト名に込められた 7つの“FIRST”の意味
-
八頭の獅子、三十七尊立体化、宝冠五仏、ガラスパーツ、礼拝空間といった 見どころ
-
一組の父娘との出会いから始まった 発願のストーリー
-
多くの寄付者と共に歩んだ 制作の歩み
また、本日より、これまで本像の造立を支えてくださったご寄付者の皆さまに、
堂内特別拝観へのご招待状を発送いたしました。
しばらくの期間は、公開のお約束を果たすために、
招待状をお持ちのご寄付者の皆様を優先的にご案内させていただきます。
本像は単なる復元ではなく、空海の構想を起点に、独自の解釈と現代の美学を融合させた「仏教美術2500年の到達点」とも言える新しい仏像です。
どうぞ特設ページをご覧いただき、この歴史的プロジェクトの全貌に触れてください。
特設ページはこちら
[THE FIRST BUTSUZO プロジェクト特設ページ]
【ご報告】大日如来像、組み立て完了のお知らせ
2025.09.18
【ご報告】大日如来像、組み立て完了のお知らせ
平素より讃岐国分寺の大日如来像造立プロジェクトに、多大なるご支援とご関心を賜りまして、心より厚く御礼申し上げます。
このたび、長らく取り組んでまいりました大日如来像の組み立て作業が、ついに最終段階を迎え、すべてのガラスパーツの取り付けを含め、主要な組み立て工程が完了いたしました。高さ約四メートルに及ぶ本像は、光を受けて輝くガラスの蓮華や光背をまとい、堂内に荘厳な光景を現しております。
発願から足かけ十五年、全国から寄せられた数万人の皆様の温かいご寄付と祈りに支えられ、ここまで歩んでくることができました。この場をお借りして、改めて深く感謝申し上げます。
現在、残されているのは細部の調整や最終的な仕上げのみであり、10月11日(土)から予定しております公開は、問題なく実施できる見通しとなっております。公開初日には、まず法要を厳修し、その後、寄付者の皆様を優先して堂内へご案内申し上げる予定です。
この大日如来像は、単なる美術作品ではなく、祈りと願いを込めて造立された「現代に甦る空海の大日如来像」であり、多くの方々に「この世界は、生きる価値がある。あなたの人生は、生きる価値がある。」という本像に込めたメッセージを感じ取って頂くことを願っております。
今後も公開に向けて最後まで責任を持って準備を進めてまいります。ご寄付者の皆様には郵便にて公開の招待状をお送りいたしますとともに、公開についての詳細な情報は、決まり次第、こちら公式サイトにてお伝えいたします。どうぞ当日を楽しみにお待ちいただければ幸いです。
合掌
讃岐国分寺 住職
大塚純司
 THE FIRST BUTSUZO ― 私が仏像に込めた想い
THE FIRST BUTSUZO ― 私が仏像に込めた想い
Ⅰ. 原点 ― 一組の親娘との出会いから
全ての始まりは、東日本大震災のあった冬、小雪の舞う寒い日。
一組のご夫婦がお嬢さんを連れて当寺を訪れました。お嬢さんは重い障がいを持ち、寝台状の車椅子に横たわっていました。救いと癒しを求めて参拝されたのでしょう。しかし、お父様の表情には深い苦悩が刻まれ、消えることはありませんでした。
その姿を目にしたとき、私は僧侶として、また寺院として、彼らが求めるものを十分に提供できていないのではないかと感じました。力不足を恥じると同時に、「救いを求める人に対して、私にできることは何か」を改めて問い直したのです。
その問いが、私を大きな決意へと導きました。――空海が構想した幻の大日如来像を甦らせること。
Ⅱ. 発願 ― 空海の構想を再解釈する
空海が構想した大日如来像は、500年前に戦乱で焼失した幻の仏像です。
私は歴史研究者としての知識と、密教僧としての修行と思想および宗教観を重ね合わせ、古文書を独自に読み解き、空海のビジョンを現代的に再解釈しました。
そして、「ただの復元」ではなく、私個人の思想と価値観および美学に基づき、空海以降から現代に至る密教思想の深化を加えた全く新しい独自の大日如来像の完成図を描きあげたのです。
これを立体化するため、私は彫刻家の工房に依頼し、10年以上にわたり、無数の具体的指示を出し続け、私の構想を忠実に形にしていきました。その過程は苦難の連続でしたが、私はただ一つの信念に突き動かされていました。――人々に希望と救いを届けたいという思いです。
Ⅲ. 密教の方法論 ― 言葉を超えるメッセージ
空海の言葉に、こうあります。
「密蔵は深玄にして翰墨に載せがたし。さらに図画を仮りて悟らざるに開示す。」
(密教の教えは奥深く難解であり、言葉や文字では伝えることができない。ゆえに絵画や仏像などのビジュアルを借りて、まだ悟っていない人々にその教えを示すのだ)
私はまさにこの方法論を実践したいと考えました。
言葉ではなく、仏像という視覚表現を通じて苦悩を抱える人々にポジティブなメッセージを届ける。それこそが、現代における僧侶としての使命であると信じたのです。
そのメッセージとは――
「この世界は生きる価値がある。あなたの人生は、生きる価値がある。」
Ⅳ. THE FIRST BUTSUZO プロジェクトとは
こうして生まれた仏像込めた想いを世界に伝えるために、私は“THE FIRST BUTSUZO” プロジェクトと名付けました。
これは単なる過去の仏像の再現ではなく、空海の構想を起点にしつつ、そのはるか昔から現在まで2500年に及ぶ仏教美術の歴史と思想を統合し、その頂点を目指す究極の仏像を生み出す試みです。
“THE FIRST” に込めた意味
-
初めての出会い – 外国人にとって人生で初めて出会う本物の日本仏像。
-
頂点としての第一 – 2500年の仏教美術史の到達点。
-
原点と再生 – 空海の幻の大日如来像を起源とし、500年ぶりに甦らせた。
-
唯一無二 – 他には存在しない、ただひとつの仏像。
-
新しい第一歩 – 伝統を継承しつつ、未来を見つめて進化した革新的な仏像。
-
普遍的な体験 – 誰にとっても一度きりの、言葉を超えた精神的な原体験。
“THE FIRST BUTSUZO” プロジェクトという名には、このような思いが込められています。
Ⅴ. 未来への展望 ― 新しい宗教活動のかたち
私の計画はこの大日如来像だけにとどまりません。
本尊である大日如来像に加え、二体の脇侍――不動明王と金剛薩埵(こんごうさった)を造立する構想を進めています。
この三尊構成は、空海が東寺で構想した「立体曼荼羅」に起源を持ちますが、
しかし私は、単なる模倣ではなく、独自の解釈を加え、これまで存在しなかった全く新しい姿の不動明王と金剛薩埵像を生み出すことを目指しています。
これは単に過去を再現するのではなく、未来に向けて進化する、これまでに存在しない全く新しい仏像を生み出す試みです。
すなわち、THE FIRST BUTSUZO プロジェクトは、新しい時代の仏像を用いた宗教活動であり、その可能性は無限に広がっています。
Ⅵ. 結び ― あなたと共に未来へ
私はこの十数年、すべての情熱をこの仏像造りに注いできました。
その原点は、一人の父と娘の苦悩に寄り添いたいという思いでした。
そしてこれから先、この仏像はすべての人々に向けて、
「この世界は生きる価値がある。あなたの人生は、生きる価値がある。」
というメッセージを放ち続けます。
どうか、この物語を共に分かち合い、未来へと広げてください。
この仏像は、あなたと共に歩むためにここにあります。
合掌
令和七年 九月吉日
四国八十番札所 讃岐国分寺
住職 大塚純司 九拝
— English Edition
THE FIRST BUTSUZO — The Vision I Placed into This Statue
I. The Origin — An Encounter with a Family
It all began in the winter of the Great East Japan Earthquake, on a day when light snow was falling.
A couple visited our temple with their daughter, who was lying in a special bed-shaped wheelchair due to a severe disability.
They came in search of comfort and healing. Yet, the father’s face remained deeply marked by sorrow and despair.
At that moment, I felt that as a priest, and as a temple, I was not offering them what they truly sought.
Ashamed of my own inadequacy, I asked myself anew: What can I do for those who come here seeking salvation in the midst of their suffering?
This question led me to a great decision — to revive the long-lost vision of Kūkai’s Great Dainichi Nyorai statue.
II. The Vow — Reinterpreting Kūkai’s Vision
The great statue once envisioned by Kūkai had been lost to fire in warfare five centuries ago.
Drawing upon my training as a historian, my life as a monk of Esoteric Buddhism, and my own religious philosophy, I re-examined ancient manuscripts and sought to reinterpret Kūkai’s vision for our time.
What emerged was not a mere “replica,” but an entirely new image of Dainichi Nyorai: a vision shaped by my own philosophy, values, and aesthetics, deepened further through the evolution of Esoteric Buddhist thought from Kūkai’s era to the present.
To give it physical form, I entrusted the work to a sculptor’s atelier. For over ten years, I continued to issue countless specific instructions, striving to ensure that my vision would be realized faithfully.
The process was filled with hardship, but one unwavering conviction sustained me: the wish to bring hope and solace to people through this statue.
III. The Method of Esoteric Buddhism — A Message Beyond Words
Kūkai once wrote:
“The esoteric treasury is so profound that it cannot be conveyed by brush and ink. Thus, we borrow images to reveal it to those not yet awakened.”
Esoteric Buddhism teaches that truth is too deep and complex to be transmitted through words alone.
Instead, it must be conveyed through visual expression — through sacred forms and statues.
This is the very method I sought to embody.
Not through words, but through the presence of the Buddha image, I wished to deliver a positive message to those burdened with suffering.
That message is simple, yet absolute:
“This world is worth living in. Your life is worth living.”
IV. The Meaning of THE FIRST BUTSUZO Project
Thus, this statue was born.
To share its spirit with the world, I named this endeavor THE FIRST BUTSUZO.
It is not the reproduction of a past image, but an attempt to create the ultimate Buddhist statue — one that begins with Kūkai’s vision, yet integrates 2,500 years of Buddhist art and philosophy into a single form, standing at the very pinnacle of that history.
The Many Meanings of “THE FIRST”
- My First Encounter – For many, especially visitors from abroad, it will be their first authentic encounter with a Japanese Buddha statue.
- The Ultimate First – The culmination of 2,500 years of Buddhist art.
- Origin and Renewal – Reviving the lost vision of Kūkai after five centuries.
- The Only One – A creation without parallel, unique in the world.
- A New Beginning – A step forward, carrying tradition into the future.
- A Universal Experience – A once-in-a-lifetime encounter that transcends language.
The name THE FIRST BUTSUZO carries all of these meanings within it.
V. The Future Vision — A New Form of Religious Practice
My plan does not end with this Great Dainichi Nyorai.
I am preparing to add two attendant figures: Fudō Myōō and Kongōsatta (Vajrasattva).
This triad echoes the Three-Dimensional Mandala once conceived by Kūkai at Tōji in Kyoto.
Yet, I will not simply reproduce the past.
Through my own interpretation, I intend to create entirely new and unprecedented forms of Fudō Myōō and Kongōsatta — statues that have never before existed.
This is not a return to the past, but a step into the future: the creation of new Buddhist images for a new age.
In this sense, THE FIRST BUTSUZO Project is more than a statue; it is a new kind of religious practice, opening limitless possibilities for the future.
VI. Conclusion — Walking into the Future Together
For more than a decade, I have poured all my passion into the creation of this statue.
Its origin lay in the suffering of one father and daughter — but its message now extends to all people.
This statue will continue to declare, to everyone who stands before it:
“This world is worth living in. Your life is worth living.”
Let us share this story together, and carry it into the future.
This Buddha exists to walk alongside you.
Respectfully,
Sanuki Kokubunji
Chief Priest
Junji Ōtsuka
大日如来像 一般公開の“予告”とご案内
2025.08.26

大日如来像 一般公開の“予告”とご案内
発願から足掛け十五年。
私たちは、多くの方の祈りと浄財に支えられながら、大日如来像の造立に歩みを重ねてきました。制作の現場では失敗ややり直しを幾度となく受け入れ、裁判という厳しい局面にあっても、約束を誠実に果たすために最善を尽くし、行を修める年月でした。ここまで伴走してくださった寄付者・関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。
本像は、言葉ではなく「見ること」そのものが教え――すなわち救いとなるという密教の方法論を、正面から体現する試みです。
弘法大師のことばに、**「密蔵は深玄にして翰墨に載せ難し。更に図画を仮りて悟らざるに開示す。」**とあります。私たちは、形相・光彩・印相・荘厳の総体をととのえ、苦難のただなかにある方にも、言葉に先立って希望が届くよう、視覚表現に教えを結晶させることをめざしました。その原点には、東日本大震災の冬、小雪の中で出会った一組のご家族の祈りがあります。弱さや痛みの側にそっと寄り添い、その生の尊さを支えたい――その願いに基づき、私は本像のすべてを定め、制作を自ら主導して参りました。
公開時期について(予告)
当山は10月中の一般公開開始を目指して、最終準備を進めております。第一候補日は10月11日(三連休初日の土曜日)です。
ただいま、関係者の知恵と総力を結集して、全力で組み立てと、その完了後に行う安全確認・拝観動線などの最終検証の準備を整えております。
最終的な日程は、これらの検証を経て「9月下旬」に公式発表いたします。
遠方よりご参拝を計画くださる皆さまにはご不便をおかけしますが、どうか今しばらくお待ちください。確定発表の際は、拝観時間等のご案内を合わせて掲出いたします。
当面の運用(寄付者優先公開について)
公開初期は混雑状況の見通しが立ちにくいため、これまでのご支援への深い感謝と、そのお約束を誠実に果たすため、当面は「寄付者優先公開」といたします。
ご寄付を頂いた皆さま(クラウドファンディングの拝観券リターンをお選びの方を含む)で、住所をお知らせ頂いている方には、公開日が確定し次第、拝観券を兼ねた招待状(ハガキ)を発送いたします。
ご参拝の際は、当該ハガキをご持参ください。同行者の可否・再入場・時間帯指定などの詳細は、招待状および公式サイトの確定告知にてご案内いたします。
※住所未登録・変更のある寄付者の皆さま向けの手続きにつきましても、確定告知時にご案内いたします。
本像に込めたメッセージ
この像が、人生の重さに押しつぶされそうな方々に、そっと救いの光を照らす存在であることを願っています。
—— この世界は、生きる価値がある。あなたの人生は、生きる価値がある。 ——
このメッセージを、説明板ではなく、尊像そのものが静かに語りかける。私はその一心で、本像の構想と制作、更なる構想の錬磨と具現化に打ち込んで参りました。
最終発表までの間も、準備の進捗を公式サイトおよびSNS(主にInstagram)でお知らせしてまいります。どうぞご自愛のうえ、その日を楽しみにお待ちください。
合掌
令和七年 八月吉日
四国八十番札所 讃岐国分寺
住職 大塚純司 九拝
【Yahoo!ニュースに寄せられたご質問へのご説明】
2025.08.03
【ご報告】高松地裁、仏像公開差止仮処分の解除決定について
2025.07.31
仏像公開遅延の理由と東京地裁判決のご報告
2025.03.06
当寺では、多くの皆様のご支援のもと、大日如来像の再現造立を進めてまいりました。しかしながら、本来予定されていた仏像の公開が大幅に遅れていることにつきまして、皆様に深くお詫び申し上げます。この度、東京地方裁判所の判決が出ましたので、公開遅延の理由と現状について、ご報告いたします。
1. 公開遅延の原因
当寺は、2013年(平成25年)に彫刻家 大森暁生氏と契約を結び、制作期間3年、契約金額3,000万円という条件で合意し、仏像の制作を正式に依頼しました。しかし、仏像の完成は大幅に遅延し、その後、ようやく仏像の引渡日を2023年8月と合意しましたが、最終的に、同引き渡し日における仏像の引き渡しが拒否されました。その間、当寺は大森氏からの度重なる追加要求に応じ、契約金額の約3倍にあたる8,184万円以上を支払ってきました。
こうした状況を受け、当寺は、仏像の引渡しを求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てたところ、大森氏は、突如、当初予定額の20倍以上となる6億3300万円もの巨額の残代金を主張するなどしましたが、2023年11月、同裁判所は、大森氏の主張を排斥し、「仏像を引き渡すべきである」との決定を下し、裁判所の強制執行により、正式に当寺が仏像を回収しました。
2. 現在も続く不当な公開差し止め
このようにして、仏像が東京地方裁判所の決定を経て引き渡され、当寺において公開の準備を進めていたところ、大森氏は、仏像の著作権等を主張し、その公開の差し止めを求める仮処分を高松地方裁判所に申し立てました。その結果、実質的な審理が行われないまま、拙速に公開の差し止めが認められてしまい、現在も公開が妨げられている状況にあります。
これに対し、今般、2025年2月28日、東京地方裁判所は、改めて「国分寺が本件仏像を開眼法要その他の方法で公に展示することは、少なくとも共同著作権者である国分寺による展示権の行使であり、大森氏が正当な理由なく合意の成立を妨げていると考えられる以上、大森氏が国分寺に対して著作権侵害を主張することは権利濫用に当たる」と判断しました。
また、東京地方裁判所は、残代金が6億3300万円あるとの大森氏の主張についても、プロジェクトの総事業費が1億3500万円であり、大森氏の報酬額は、そこからお堂の改修費用等(5000万円超える)を控除した残額に止まるとの共通認識があったことや、大森氏も、計4000万円を受領した2020年10月の時点で、「すでに予定を大幅に上回る製作資金を受領している」と述べ、その受領額ですら過分なものであると認識していたこと等を踏まえ、すでに支払われた8000万円以上の金額をもって、製作費相当額の代金は支払われていると認定し、大森氏の残代金に関する主張を排斥し、併せて、仏像の所有権も当寺にあると判断しました。
この東京地方裁判所の判断を踏まえ、高松地方裁判所においても、早期に同様の判断が行われ、不当な公開差し止めが解除されることが強く期待されます。
しかしながら、この不当な公開差し止めの申し立てによって、当初の公開予定日であった2023年10月7日からすでに約1年半が経過しています。その間、ご寄付者の皆様の中にはご高齢の方も多く、公開を楽しみにしていたにもかかわらず、仏像を見られぬままご逝去された方も多数おられます。この取り返しのつかない被害が今なお続いており、深く憂慮すべき事態です。
さらに、当寺には今なお仏像の公開についての問い合わせや苦情が日々多数寄せられており、多くの方々が公開の実現を切望されています。当寺としても、これ以上の遅延によって支援者の皆様の期待を裏切ることのないよう、速やかに公開を実現するため尽力しております。上記のとおり、その成果が今回、東京地方裁判所の判断として示されており、当寺は、今なお続く、高松地方裁判所の公開差し止めを速やかに解除して頂きますよう、誠心誠意、対応を継続して参ります。
3. ご支援いただいた皆様および報道関係の皆様へ
本件仏像は、単なる宗教的な対象にとどまらず、数万人ものご寄付者の想いが込められた貴重な文化財であり、その公開は広く社会の利益に資するものです。当寺は、仏像の公開を通じて、皆様のご支援に感謝の気持ちを表し、地域の文化と信仰の場を守ることを使命としております。
しかしながら、大森氏による一方的な契約違反と法的な妨害により、公開が妨げられている現状を、どうかご理解いただきたく存じます。当寺は、裁判所の判断に基づき、正当な権利を行使し、仏像の公開を実現するための法的対応を誠心誠意、続けてまいります。皆様の温かいご支援とご理解を賜りますよう、何卒、お願い申し上げます。
また、マスコミ・報道関係者の皆様におかれましては、本件仏像と裁判に関わる全ての情報を開示し、いかなる取材要請にも誠意をもってお答えする所存です。それはこれまでも、これからも変わりません。本件を報道いただき、真実を広く世間に周知することで、仏像公開を一日も早く実現させたいと考えております。
4. 最後に
本件は、契約の履行と所有権、さらには著作権の適正な行使という極めて重要な法的問題を含むものでした。東京地裁は、双方の証拠を厳格かつ公正に評価した上で、法の原則に則り、公正かつ慎重な判断を下し、権利の濫用が認められないことを明確に示しました。
この判断は、契約の誠実な履行を求める社会全体の信頼を守るものであり、また、日本国憲法において保障された信仰の自由という極めて重要な権利が、いまなお不当に制約されている現状を踏まえれば、単に一つの裁判の結論を示すものにとどまらず、法律の持つ本来の意義を改めて浮き彫りにするものであります。
法律とは、人々の権利を守るために存在し、その適正な運用こそが、社会全体の秩序を維持し、人々の心の安寧を保つための基盤となるものです。今回の判決は、まさにその根幹をなす役割を果たし、法が社会の公正と調和を支えるものであることを改めて証明しました。
私たちは、これまで法の適正な運用を信じ、その公正な判断を待ち続けてまいりました。今回の東京地裁の判断により、その信頼が正しかったことが示され、深い感謝と敬意を抱いております。
当寺は、この東京地裁の判断を尊重し、引き続き法の適正な運用のもと、仏像公開に向けて誠心誠意、対応を進めてまいります。今後、高松地裁においても、東京地裁が示した法的原則に則った、正当かつ適正な判断がなされることを強く期待しております。
合掌
讃岐国分寺住職 大塚純司 九拝
令和七年の初詣のご案内
2024.12.27
初詣のご案内
令和7年の初詣に向けまして、顔出しパネルを設置いたしました。
来年の干支は乙巳(きのと み)です。巳=蛇は古来より弁財天様のお使いとされておりますので、当山がお祀りしている弁財天様をイメージした女の子のキャラクター、弁財天のサラちゃんと白蛇をデザインしました。顔出しの部分は白蛇の赤ちゃんです。
乙(きのと)には若木が成長するという意味があることから、新緑色の文字を採用しています。
このような素敵な顔出しパネルが出来上がりましたので、ぜひ、初詣にご来山頂きまして、ご家族、ご友人と一緒に記念撮影して頂ければ幸いです。お子さんの成長記録してもご家族の記念の一枚になると思います。
また毎年恒例となっております、初詣記念授与として、お守りお札類を3千円以上お買い上げの方に、干支をテーマにデザインした当山オリジナルのA4サイズコットンバッグをプレゼントしております。こちらも、顔出しパネル同様、弁財天のキャラクターと白蛇をデザインいたしました。乙巳のテーマカラーである黄緑色でプリントしております。なお、数に限りがございますので、コットンバッグをご希望の方は早めにお越しくださいませ。
きのとみ(乙巳)の年は、努力を重ねて物事を安定させていく年とされています。また、成長と結実の時期となる可能性が高く、これまでの努力や準備が実を結び始める年ともいわれています。
きのとみ(乙巳)の「乙」は十干で第2番で、しなやかに伸びる草木を表しており、困難があっても紆余曲折しながら進むことを意味します。「巳」は植物が最大限まで成長した状態を意味し、これまでの努力や準備が実を結び始める時期を示唆しています。
巳(へび)は古代から再生や永遠の象徴とされ、皮を脱ぎ捨て新たな姿に生まれ変わる姿がその象徴となっています。こうした意味から、巳年は新しい挑戦や変化に対して前向きな姿勢を示す年とも解釈されています。
国分寺の建立を発願した聖武天皇の願いを今なお受け継ぐ当山は、護国安民の寺として、令和七年が我が国と皆様の心身が安らかで、楽しく、成長の年となるよう心より祈念いたします。どうぞ新年のご参拝に讃岐国分寺にお越しくださいませ。 合掌
南無大師遍照金剛
讃岐国分寺住職 大塚純司九拝
特別御朱印/オリジナル御朱印帳のお知らせ
2024.05.23












